これは、私が民芸品やルビー、サファイヤなどの色石を買いつけるために、チェンマイを頻繁に訪れているうちに縁あって知り合い、後に私の親友となったタイ人のダムロンとその家族の話である。
彼の波乱万丈の人生はいまだに続いており話は完結してないが、彼と知り合ってから41年の途中経過として、この話を記することにする。【蘭菜太郎】
>>>登場人物紹介
≪注≫本文中に登場する人物などは、すべて仮名です。また、写真と本文とは一切関係ありません。【ガネッシュ】
第11話:メーサーイでの商談
翌日は、朝からメーサーイに宝石を見に行くことになった。
メーサーイの街の裏通りには、軒先にテーブルなどを置いて、主にビルマ(ミャンマー)から国境を越えて持ち込まれる、ルビーやサファイヤをはじめとする色石の原石を買い取る仲介業者がたくさんいる。表向きには、こうした仲介業者は買い取り専門で、小売りは原則としてしない、ということになっている。しかし、外からだとすべて個人営業のように見える彼らではあるが、実際には半数以上がオーナーに雇われている買い付け人である。よい石を安く買い取れれば歩合がよくなるわけだが、たとえ買い付けに失敗したとしても、自分が損害を被ることはない。そこで、オーナーに内緒で、買った原石の一部を横流しする者が出てくるのである。つまり、買い取った原石の中に適当な掘り出し物が見つかると、それを自分のものにしてしまうのだ。
このような横流しの原石は、大抵の場合は買い付け人の奥さんや家族が持ち歩き、宝石店などに毎日のように出入りして、よい値で売れる機会を狙っている。ファラン(欧米人)や私のような日本人などは、後腐れのないバイヤーということで、こうした宝石の販売先としては最も都合のよい相手、というわけだ。
こういった取引では、相手が売り急いでいる時にはかなりの値引きも可能だが、ダメな時はぜんぜんダメと浮き沈みが激しい。長期間滞在すれば、情報を集めたり知り合いを作ることも可能なのであろうが、ポッと出ではなかなかむずかしい。
メーサーイの大通りの、国境近くにある小さな宝石店をひやかしながら歩いていると、それらしいおじさんが近づいて来た。おじさんに目で合図して、店の裏手へ歩いて行くと、案の定後からついて来て、懐から原石の入った包みを取り出してくる。
このような場合、最初から上物を出すことはまず有り得ない。はじめに見せるのは、クズ石かニセ物である。売り手にしてみれば、そうしたほとんど無価値の石が売れるのならば、それに越したことはないのである。思った通りに、おじさんが最初に出した包みは、ルビーの原石コランダムのクズ石ばかりであった。そんなものを買ってもどうにもならないので、「ほかにないのか? 全部見せろ」とやっていると、よそを回っていたダムロンがやって来て、宝石をのぞき込んでいる。そこで、おじさんが恭しく取り出したのは、小指の先ほどの大きさのルビーのまだカットしていない裸石で、これはかなりのクオリティーのものであった。
17カラットだという、濁ったチェリーピンクの石の一部に開けてあるのぞき窓から、石の内部を見る。すると、内部は見た目よりさらに上物で、理想的なルビーの色に近い、鮮かなチェリーピンクをしている。肉眼で見た限り、目立つ不純物もほとんどない。ポケットから、郵便物の重さを計る小さな秤と10倍鏡レンズを取り出し、石を痛めぬようにそっとピンセットではさみ、重さを計る。このような小さな秤や検出器は、宝石の買い付けでは必需品である。最近は、とてもよくできたニセ物もあるので、油断できない。3.5g弱、確かに17カラットくらいである。
一度、そっとピンセットからはずし、10倍鏡レンズでさらに詳しく内部を見る。売り手は、買い手のこういった手際をよく観察して言い値を決めてくるので、プロらしく振る舞わねばならない。
私がまだ何も言わないうちに、ダムロンが「これはいくらだ?」と聞いている。「ヌンセーン・ハームン(15万)」とおじさんが言うと、ダムロンは大いに驚いた。「15万バーツだって?こんなものがそんなに高いわけがない。お前は頭がおかしいんじゃないのか?」とか言っている。確かに15万バーツは高いが、このクオリティーであればそんなにべらぼうな値段でもない。私は、「それはそちらの希望価格だろう。町の宝石屋でもその値段ならばカットしてある石が買えるぞ。どのくらい値引きできるんだ?」とたずねると、オドオドとダムロンの方を見ながら、小さい声で「少しだけなら」と言う。「少しじゃダメだよ。うんと値引きしないと、買わないよ」と言い、「カラットあたりが3,000バーツで5万バーツ、大きい石だからその倍くらい出してもよいが、10万バーツくらいで買わないと、こちらの儲けがなくなってしまうよ」と、ハッキリ自分の意思表示をする。
おじさんは、両手のひらをこちらに向け、激しく横に振って、「そんなに安くは売れない」と拒否している。すると、ダムロンがおじさんの前に回り込んで来て、「オイ!10万バーツでそいつを売れ!今すぐ売れ!!どうしても売れ!!!」とか言いながら、おじさんの肩や胸を押すようにこづきはじめた。小柄なこのおじさんは、たちまち板塀まで押されてしまい、それ以上後ろに下がることもできずに、ダムロンの視線をさえぎるように、両手のひらを顔の前に持っていき、防御に懸命になっている。売り手と買い手の希望価格が違いすぎ、とても交渉が成立しそうもない。私はすぐにあきらめ、ルビーをおじさんに返し、「10万バーツ以上は出せない」と言う。おじさんは、ダムロンを上目遣いでビクビクしながら見つめ、「ダメだ」と身振りで答える。交渉不成立である。
私はあきらめて表通りの方へ歩いて行ったが、後ろからダムロンがついて来ない。「まだ何かもめているのかな?」、と戻ってみると、何とダムロンはおじさんの首を両手で締め上げていた。「オイ!売るか!!売るよな?」とか言いながら、おじさんを板塀に押しつけ首を締めている。足が地面から離れそうなくらいに首を締め上げられ、おじさんは声も出ない様子である。「おいおいダムロン、そんなことをしちゃダメだよ。それでは、値引き交渉じゃなくて完全な恐喝だよ」と言いながら、ダムロンのズボンのベルトを引いておじさんから引き離す。おじさんは肩でゼイゼイと息をして、恐怖で引きつったような顔をしている。おじさんから引き離されたダムロンは、なおもおじさんを凄い目でにらんでいる。ダムロンの背を押して、表通りの方へ連れて行く。「ダムロンよ。お互い商売でやってるんだから、あんなやり方はダメだよ。あんなことをしたら、まとまる話もまとまらなくなってしまう。短気は損気、商売は気長にやらなくてはダメだよ」と言って聞かせる。ダムロンは犬のような唸り声をあげながら、まだ裏手の方をにらんでいた。
その日は、夕方近くまでメーサーイをぶらついたが、結局はその後も大した買物はなかった。チェンラーイのホテルへ戻り、さっきのダムロンの値引き交渉の話を一郎にすると、彼は腹を抱えて大笑いした。
この時は、こうした数日間のチェンラーイとメーサーイへの旅となったが、実に楽しい思い出であった。

















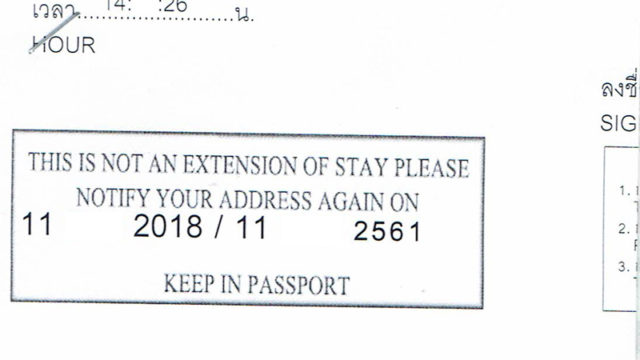





コメント