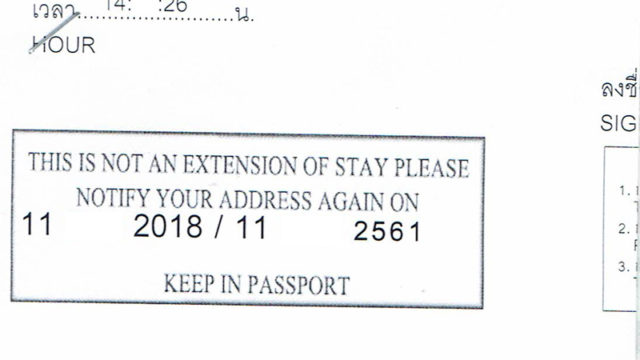第5話:不思議なパーティー
そのお祝いのパーティーは、実に楽しかった。友達も近所の人も来るとは聞いていたが、その人数には驚かされた。いや、その前に、昼過ぎにダムロンの家に行った時に見た食料品の山にまず目をむいた。
タライよりも大きなアルミの入れものに、肉や卵がまさしく山のように積まれ、所狭しと置いてある。それはもう、人間の食べるものとは思えない量であった。「これを全部食べるのか?」とたずねると、「来る人数によっては、足りないかもしれない」とダムロンは言う。要するに、来る人数をきちんと把握していないのである。これは、余ったら動物園にでも引き取ってもらわなくちゃならないんじゃないかと、ひとごとながら心配になってきた。
ティップが、肉を焼くための四角い金火鉢に炭をくべながら、支度を手伝っている家族や近所の人に手順を指示している。ケオは、ドラム缶のカマドに乗せた金ダライで卵を茹でていた。ソムサックと奥さんのニンが、肉を小さく切っている。ダムロンは、ものすごく辛そうな焼き肉用のソースを作って、その出来栄えを盛んに自慢していた。
夕方の5時近くになると、近所のおばさん達が次々とやって来て、料理の支度を手伝い始めた。膨大な量の茹で玉子の殻がむかれ、肉が次々とバーベキューにされていく。
肉が焼けてよい香りを立て出したのを見計らったように、近所の人達がドッと現れた。料理が配られ、酒が振る舞われる。子供たちには大きなケーキがカットされて配られ、飲み物の栓がポンポン抜かれていく。
どんどん客が増えて、もう足の踏み場もなくなった頃にケオがやって来て、「カジノを見に来い」と言う。「何だ、そりゃ?」と見に行くと、ケオの家に人が集まって、即席の賭場を開帳していた。こんなバラックに大勢の人が入って壊れないのかな、と心配になるほど、そこにはたくさん人が詰めかけていて、トランプやタイ式花札の小博打をしたり、それを見物しながら飲み食いしており、末弟のゲアッとソムサックの奥さんのニンが、お客に酒や料理を配っていた。そして、よく見ると、そこにはここに遊びに来た時に見かける近所の人達が大勢いた。
ダムロンから、友達だと紹介されたブン。しかし、友達というよりは子分か弟分といったカンジで、常にダムロンと行動を共にしている人だ。やはり、職業は不明。彼は、ダムロンの家の隣の敷地の一角にあるバラックを借りて、夫婦で住んでいる。半ズボンの尻ポケットにいつも強力そうなパチンコを入れている、変わった人である。博打を見物しながら酒を飲み過ぎ、わけのわからぬ罵声を張り上げて周りの人に迷惑がられているのは、すぐ裏に住んでいるというご隠居さんだが、私はこのおじいさんが酒に酔っていないところをついぞ見たことがない。博打に興奮して一際大きな声を出しているのは、やはり以前ダムロンから紹介されたことのあるウイラット。彼はインスペクター、つまり警察官である。彼の存在が、ダムロンをさらに不思議な人にしており、このウイラットが何らかの力をダムロンに与えているのではないか、とも考えた。
夜の7時頃になると、もう家も庭も人であふれ返り、移動するのも大変な騒ぎとなってきた。ダムロンの家の高床の下にある、くつろぎの場に置かれている縁台まで何とかたどり着くと、そこには乳飲み子を抱いたティップとダムロンが、皆に取り囲まれるようにして座っていた。そして、そのすぐ隣には、背もたれのある椅子に座った産後のボアライとダムロンの母親がいた。
ダムロンが私に声をかけて来て、自分の右横の床を叩き「ここに座れ」と言っている。そこは縁台の中央であるため、人混みで脱いだ靴がどうなるか心配だったので遠慮した。「パーティを見たいから」と言って、人並みをかき分けながら敷地の入口に行くと、人が家の前の通りにまであふれ出しており、大勢の人が楽しそうに飲み食いしているのが見えた。
私は、このような形式のパーティーに参加するのは初めてであった。全く知らない人はいないのだろうが、誰でも来た人に酒や食事を振る舞うのは、日本では選挙事務所くらいなもので、個人的な祝い事ではまず考えられないのだが、現にここではそうしていた。私が以前住んだことのあるインドなどでは、2千人とか3千人とかが来る結婚式もあるにはあるが、その場合だって、すべて招待状を持っている人だけであって、こんなに無秩序ではない。
私は、うれしくなってしまった。来ている人々はみんな普段着であり、特にめかし込んでいる人など一人もいない。しかも、これだけの人数を呼んだのに、ホストのダムロンやティップも普段着のボロを着たままなのだ。
それは、タイの人々のおおらかさと謙虚さを如実に見たような光景であった。
しかし、後になってから、単純にそれだけではなかったことがだんだんとわかって来るのだが、少なくともこの時にはそう感じられた。そして、この人達と友達になり、この沢山の人達の仲間になれたことの幸運に、感謝せずにはいられなかった。